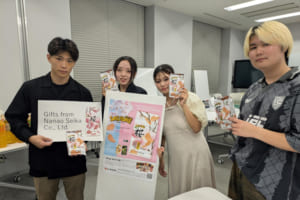2025年7月19日(金)・20日(土)、九州国際大学(北九州市)にて「第4回持続可能な開発とグローバル社会に関する国際会議(ICSGS 2025)」が開催されました。本会議は、インドネシア大学(Universitas Indonesia)と九州国際大学の共催により実施され、両大学の学術的連携を象徴する重要なイベントとなりました。
会議には、インドネシア各地の大学からの研究者を中心に、100名以上の研究者がオフラインで九州国際大学に集い、さらにオンライン参加者も交えてハイブリッド形式で開催されました。環境、経済、教育、文化交流、ハラール産業など幅広い分野にわたり、「持続可能な開発」という共通テーマのもと、活発な研究発表と意見交換が行われました。
開会式では、共催機関や関連団体からのメッセージが紹介され、国際的な学術協力の重要性と今後の発展への期待が述べられました。
北九州市からは、産業経済局および環境局の担当者が登壇し、市の国際ビジネス戦略や環境・産業政策の海外展開について具体的な取り組みを紹介しました。これらの報告は特に興味深く受け止められ、これまで東京や大阪に集中し福岡まで足を伸ばすことのなかったインドネシアの研究者たちが、北九州の持つ潜在力に注目するきっかけとなりました。
初日の基調講演では、アジア成長研究所の八田達夫氏が登壇し、北九州空港の滑走路延長と24時間運用の必要性を提言しました。福岡空港との機能分担により、北部九州の経済成長を後押しできるとの構想が語られました。
続いて、インドネシア大学のI Ketut Surajaya教授が、日本とインドネシアの関係について、歴史的背景をふまえつつその多層的な意義に光を当てました。
二日目には、ユトレヒト大学の大築圭教授が登壇し、インドネシアの新首都「IKN」を題材に、スマートシティの視点からその特徴と課題を掘り下げました。
また、久留米市に本社を置くAAI株式会社の中村廣秀会長からは、両国の経済発展に資する協力の可能性について、実例を交えながら具体的な提案がなされました。
本会議では、日本やインドネシアをはじめ、パキスタン、エジプト、バングラデシュ、中国、オランダ(ユトレヒト大学)など、多様な国籍の研究者による発表が行われました。
国際会議の参加者のほとんどがイスラム教徒であったこともあり、ハラールに関する2つのパネル報告は特に注目を集めました。中でも、ムスリム多数派国の厳格なハラール基準およびその運用制度の妥当性や正当性を問い直す内容が複数含まれており、これが制度の見直しを促す学術的議論を活発化させました。こうした報告は会場の研究者に強い刺激を与え、今後の研究や政策に向けた重要な示唆を提供しました。
参加者の多くは隣接するJICA九州センターに宿泊され、昼食には地元の仕出し業者によるハラール対応弁当が提供されました。1日目の夜は千草ホテルにてバンケットが開催され、北九州邦友会の日本舞踊、プレゼンターの一人であるAhmad 前野氏によるアラビア語のナシード披露、九州国際大学ダンスサークルのパフォーマンスなど、多彩な文化交流が行われました。会議の日程が地域の祇園山笠祭りと重なったため、参加者は太鼓や鐘の音を響かせながら練り歩く山笠を垣間見ることができました。また、夜には「日本一の夜景」と評される皿倉山からの夜景観賞も実施され、参加者には北九州の魅力を存分に味わっていただけたと思います。
空港への出迎え、受付業務、会議の運営、司会(一部)、ティーラウンジの提供など、本会議の運営に関わる多くの実務は、九州国際大学の学生たちの協力なしには成し遂げられませんでした。学生たちは、国内外からの来訪者に対し、温かく丁寧に対応し、多文化共生の現場を支える貴重な経験を積む機会ともなりました。
2日間にわたる本国際会議は、登壇者・参加者ともに熱意あふれる交流が繰り広げられ、学術面だけでなく地域文化や経済との結びつきも深める意義あるものとなりました。今後も九州国際大学は、国際的な学術交流と地域連携の促進に努め、持続可能な経済発展と多文化共生に寄与してまいります。